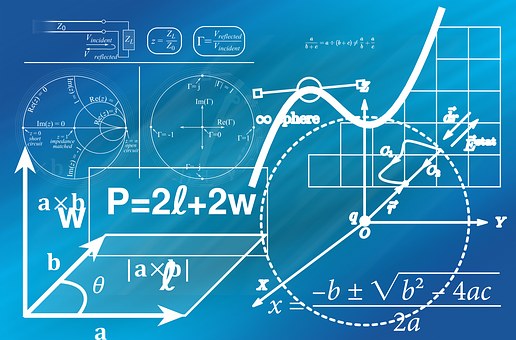「科学の条件とは(2)再現性について」では、「それを〈科学〉と呼べるのか」を裁定する基準としてよく触れられる「再現性」について論じました。

今回も科学の条件に関する話題です。
霊や魂について議論していると、よく「そんなの〈証明〉されていないだろう」「あると言うなら科学的に〈証明〉してみろ」などという声が聞かれます。
実はこの〈証明〉という概念がかなり曖昧で曲者なのです。
この概念が都合よく使われて、未知の現象を排除する理由にされているようなので、少しコメントしてみたいと思います。
一口に「証明」と言っても……
この「証明」という言葉は、とても曖昧で多義的です。
例えば、数学や論理学といったジャンルなら「証明」の意味も分かりやすいかもしれません。
中学や高校で数学の証明問題をよくやらされましたが、ああいうやつですね。確かにあれは誰が見ても確実な証明と言えるでしょう。
しかしこれが自然現象を相手にする科学となると、「証明」という概念の意味は途端に曖昧になってしまうのです。
理論物理学の一部など、小さな範囲では数学に近い証明ができるものもあるかもしれませんが、それは自然科学全体のごくごく一部に過ぎないでしょう。
例えば、宇宙の始まりにあったと言われている「ビッグバン」……。
これが実際にあったことって〈証明〉されているのでしょうか?
少なくとも、ビッグバンを直接見た人はいません。
でもビッグバンが起きたことは、その痕跡とも言われる電磁波(宇宙背景放射)の存在など、いくつかの間接的な証拠から「最も合理的な推論」として導き出されているようです。
もちろんそれを「証明」と呼ぶならそう呼んでも構わないと思いますが、頑固な人がいて「ビデオでその事象を録画して全員で確認しなければ証明じゃない!」と言うなら証明ではないでしょう。
科学なら実験や観察によって証明できるのではないかと思われるかもしれませんが、実はそれほど単純な話でもないようです。
科学史を振り返ると、同じ監察結果・実験結果を前にしても「その結果からどんな事実が証明されたと考えるか」が人によって異なるということがザラにあるのです。
単純な例を挙げます。
望遠鏡で月の表面を見ると凸凹が見えます。この「凸凹が見える」というのが観察結果ですね。
現代の僕たちなら、この観察結果から「月の表面は実際に凸凹している」と解釈し、そのことが証明されたと考えるでしょう。
しかし、これは実際にあったことですが、「月は完璧に美しい天体だ」という強い信念を持っている昔の人が望遠鏡で月の凸凹を観察した際、彼らは違った結論を導き出したのです。
彼らは何と「望遠鏡は(地上は正しく映すが)月に向けると正しく機能しない道具である」と解釈したのです‼
つまり背景としてどんな知識・理論・信念を持っているかによって、同じ監察結果・実験結果を前にしても「どんな事実が証明された」と解釈するかは異なってくるというわけです。
これを専門用語で「理論負荷性」と言います。
理論負荷性については以下参照。
↓↓↓↓↓↓

上の例は現代では極端に聞こえるでしょうが、本質的にこれに似た話は科学の歴史でよく出てくるのです。
「証明」も程度の問題
確かに、その他の理論や実験も踏まえて総合的に考えるなら、「誰がどう考えてもこのようにしか解釈できない」というものもあるでしょう。
そのレベルになれば物理法則として確立されていくのだと思います。
ただし、ニュートン物理学が相対性理論に置き換えられたように、どれほど確かに思える法則でも覆されたり大幅に修正されたりする可能性は常にあります。
一方、まだまだ人によって解釈が異なるグレーゾーンもあるはずです。
そのグレーゾーンの中でも、「かなり多くの科学者に支持されている解釈」とか「評価が分かれている解釈」など確実性に程度の差があるでしょう。
つまり「証明された」「証明されていない」の二分法ではなく、かなり確かなものからグレーなものまで証明の程度はグラデーションになっているのです。
そして、確実性のグラデーションの下の方にある学説、まだ異論が多くて議論が続いているような学説であってもそれを直ちに排除していては科学になりません。
例えば、超ひも理論、タイムトラベル説、異次元世界の理論、マルチバース理論、ダークマターやダークエネルギーの“正体”についての様々な説……。
現代の物理学ならこれらの説がそれに当たるでしょう。
これらの中には、将来の研究によって確実性が上がってくるものもあれば、反対に下がっていくものもあるかもしれません。しかし、そういうプロセスを経て科学は発展していくはずです。
超常現象の多くについては、学校で習う物理法則と比べると確かに「まだまだ証明の程度が低い」ということは僕も認めます。
しかしそれは「程度の差」であって、これからの研究の進展によっては確実性が上がってくることもあり得るのです。
つまり「ここから上は〈科学〉だ」「ここから下は〈疑似科学〉だ」と言ってきれいに線引きできるものではありません。
どこかで勝手に線引きしたとしても、研究の進展によってその線をまたいで上下することもあり得るのですから、その恣意的な線引きに大して意味はないでしょう。
超常現象などの研究を「科学とは何か本質的に異なるもの」と考えて拒否しようとする姿勢がアンフェアである理由もここにあります。
それについては「学校で習うような物理法則ほどに十分に裏付けされているわけではないが、研究の余地のあるもの」として態度保留すればいいだけです。
それなのに、どうして最初から排除しようとするのか、僕は理解に苦しむのです。
「霊が存在する」は証明済み
先ほど「超常現象の多くはまだ証明の程度が低い」と言いましたが例外もあります。
例えば「霊が存在すること」がそうです。これは20世紀の後半から続く「臨死体験」研究などによって解明されてきました。
これは「偏見なしで証拠を分析するならば、誰がどう考えてもそうとしか解釈できない」という意味で、かなり確実に立証された物理法則と同じようなレベルで「証明されて」います。
例えば病院における手術などの際、「脳活動の停止が客観的に確認されていた(=意識があり得ない)患者が臨死体験をし、その間の手術道具の配置や医師たちの会話などを意識回復後に詳細かつ正確に描写した」というケースがしばしば報告されます。
当然ですが、脳活動が停止していたのですから、通常ならばその間の出来事を「見る」「聞く」「記憶する」といったことは不可能です。
こうした事例は「脳活動が心や意識を生む」と考える唯物論では説明不可能であり、手術中に霊が肉体を抜け出して周囲の様子を観察していたと考えるのが最も合理的です(本人たちもそう言っているのですしね)。手術室ではなく遠隔地の様子を言い当てたケースもあります。
つまり「霊という実体があり、それは肉体から離れても活動できる」ということは以上のことだけで「証明終了」というわけです。
もちろん、唯物論の人たちは何だかんだと理由をつけてこれを〈証明〉とは認めたがりません。しかし、医師および病院スタッフの証言もあればカルテなどの治療記録も残っているわけです。
それによって「脳活動が完全に停止していたこと」「意識喪失の前後に患者が手術器具を見ていないこと」などは確認されているのです。
それでもあくまで「それは嘘だ!」と言い張るなら、その患者および病院の関係者たちが共謀して嘘をつき、カルテの偽造など時間と労力のかかる作業をしたと言っていることになります。
そこまで言うならば、「ネイチャー」などの一流の科学誌に載った実験もすべて(間違いなのではなく)自覚的な嘘だと主張するくらいの懐疑主義でないとフェアではないでしょう。
もちろん、分かったことは「肉体とは別に霊というものが存在する」ということくらいです。
それを越えて「霊とはそもそもどんな材質もしくはエネルギーでできているのか」「どんな法則に従って活動するのか」などはまったく不明です。
しかしダークマターやダークエネルギーだって現時点(2025年)では正体不明でありながら、それが「存在する」ということは認められているのですから、詳しいことが不明であるからと言って否定する理由にはなりません。
以上、今回の内容をまとめると……
超常現象などについては「証明してみろ」とよく言われますが、それに対しては「どういうことを示せばあなたの言う〈証明〉になるのですか?」と反問できます。
科学として認められているものだって〈証明〉の内実はいろいろで、それがどの程度確実であるかはまちまちなのです。
さらに……
霊が存在することなど、超常現象と呼ばれるものの一部については、確立された物理法則と同程度には証明されています。
今回は触れませんが、霊の存在以外にも「UFO・宇宙人の地球来訪」「一部のESP能力の実在」などは「証明済み」と見なしてよいと僕は考えています。
というわけで、〈証明〉云々ということを科学の条件として持ち出して、現在主流となっている研究以外のものを「非科学」「疑似科学」として排斥することが単純かつ乱暴であることは明らかです。
「科学の条件(4)反証可能性ってなに?」では、やや専門的な議論ですが、科学の特徴としてよく言及される「反証可能性」というものについて考えます。