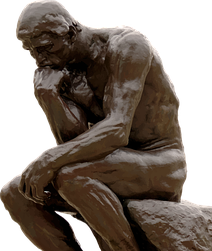前回の「デカルト(2)神と世界の存在を語る」では、「我思う、ゆえに我あり」で自分の精神の存在を証明したデカルトが、次に「神の存在証明」「外界の存在証明」へと進んだことを見ました。

外界の存在証明とは、「自分が見ている世界は幻ではなく実際に自分の外部に存在している」ということの証明です。外部世界にはもちろん自然界も含まれます。
外界の存在を証明した(と考えた)ことで、いわゆる自然科学の研究にも力が入ります。デカルトは自然科学者としても一流の業績を遺しています。
今回は、哲学の研究でも自然科学の研究でも共通している、いわば「デカルト流思考法」とはどういうものかを解説します。
合理的思考法① 4つの規則
デカルトはまず自らの思索を導く際のルールとして、「4つの規則」というものを挙げています。
①明晰の規則
明晰で疑えないものだけを真理として受け入れる。
②分析の規則
対象を小さな部分に分けて考える。
③綜合の規則
単純なものから複雑なものへと思考を進める。
④枚挙の規則
見落としがないように数え上げる。
①明晰の規則(明晰なものだけを真理とする)というのは、数学の公式などが典型的ですが、それが真理であることが人間精神にとってハッキリと(明晰に)感じられるものは受け入れるということです。
世界が存在することもいったんは疑いましたが、外界の存在証明が為された後なら、ハッキリと見たり聞いたりできるものは真実そこにあると考えていいでしょう。
②分析の規則と③綜合の規則は、小さな「部分」からまず探究し、それを理解してからそれらの合計である「全体」への理解へと進むという思考の順序を表しています。
④枚挙の規則は「大事なことを見落とさないように」ということなので、分かるでしょう。
デカルトはこの「4つの規則」を念頭に置きながら自分の思索を展開していったというわけです。
合理的思考法② 数学的思考法
デカルトに特徴的なこととしてもう1つ挙げるべきは「数学的思考法」です。
デカルトは3次元の物質世界に存在するあらゆる物体の本質は「広がりを持つこと」だと考えました。「広がりを持つ」ということを専門用語で「延長する」などと言います。確かに物体とか物質とかいうものは、タテ・ヨコ・高さという3方向に広がっています。
そしてここが大事ですが、広がりを持つものは(単位を定めさえすれば)数字を使って表現できるのです。
このビンやあのイスなど、およそ物体というものは、すべて寸法を測って数字を使って大きさなどを表すことができます。
デカルトは「X軸ーY軸」などを使って空間自体も数値化しました。これが「デカルト座標」です。こうすれば物体の運動ですら数字で表すことができます。
これが科学史上の大革命だったのです。
質量・距離・時間・速度……これらをまず数値化して、お互いの関係を調べてみるとそこに「規則性」「法則性」を見出すことができる!
近代科学が発見した多くの自然法則は、こうした数学的手法の活用によってはじめて明らかになったと言えます。近代になってから科学が急加速度的に大発展した理由の1つがこれです。
もちろん、古代の科学者だって数学を使っていましたし、デカルトより少し年上のガリレオも数学を応用しながら自然界の解明を進めていました。
しかし数学的手法の大切さというものを哲学的に思索し、それを明確に方法論として打ち出したのはデカルトです。
現代では「科学は数学的に進めるべきもの」というのはほぼ常識になっていますが、それを常識にするのに大いに貢献したのがデカルトなのです。
世界は「機械」なのか?

さて、デカルトの考え方を整理すると……
A 自然には(数学で表現できるような)一貫した法則性がある。
B 世界にあるものは何であれ小さなものの組み合わせからできている。
こう整理してみてあなたは何をイメージするでしょうか? デカルトの念頭にあったのは「機械」です。
機械仕掛けの時計を思い浮かべるとよいでしょう。小さな歯車やネジなどの小部品がたくさん組み合わさり、それらが規則的に働くことでカチコチ動く時計というものが成立していますよね。
デカルトは僕たちの生きる自然界は大きな機械のようなものだと考えました。
彼の時代にそこまで分かっていたわけではありませんが、世界は確かに、素粒子→原子→分子→高分子→……というぐあいに、より小さなものの合成から成り立っています。
そして各部分は一貫した物理法則に従っています。
そういう側面を見れば、世界は機械のようだという考えにも一理あります。現代の科学者も大枠ではこうした発想を持っているのではないでしょうか。
このように、自然を機械のようなものだと考える思想を「機械論」と言います。
自然とは「小さな部品から成り、それらが法則に従って動くだけの機械」だということです。
この機械論ですが、デカルトの友人でもある思想家メルセンヌも支持していました。
また「社会契約論」を説いたことで有名なイギリスのホッブズも同時代の人であり、ガチガチの機械論者です。
実はホッブズはフランスに亡命していた時期があり、デカルトやメルセンヌとも交流していました。機械論は彼らの知的サークルにおける中心的な主張だったと思われます。
ホッブズについては以下の記事を参照して下さい。

さて、デカルト哲学において最初に確認されたのは「考える我」が存在することです。つまり「私という精神」が存在することです。
これは「物体」とは違って、タテ・ヨコ・高さの方向に「広がりを持つ」(延長する)ものではありません。精神の本質とは「思考する」ことです。
したがって、自然界は大きな機械なのですが、そこにいる人間の精神だけは機械とは根本的に別カテゴリーの存在であることになります。
デカルトは「人間精神とは物体や機械とは根本的に異なる何かである」と考えていたので、唯物論者ではありません。
もし「人間もまた物体(肉体)以上のものではない」と主張するならデカルトは唯物論者であることになりますが、そうではないのです。
しかし、もしデカルト哲学から人間精神という〈異物〉を取り除いてしまえば、残りの世界には機械(物体)しかありません。「世界には物体しかない」というのがいわゆる唯物論の考え方です。
この意味で、デカルト的な機械論から唯物論まではもうあと一歩です。(僕たちには驚きですが)デカルトは動物ですら機械だと考えて、そこに魂が宿っているとは考えませんでした。
こうなると「動物ですら機械にすぎないなら、人間だけ特別扱いする必要はない」と考える思想家が出てきても不思議ではありません。
後世、人間もまた機械だと説く「人間機械論」が実際に登場してきました。ここまで来ると完全に唯物論ですね。

繰り返しになりますが、デカルト自身は人間精神は物体とはまったく異なる存在だとして、肉体が滅びた後も「魂」として存続すると考えていたようなので、決して唯物論者とは言えません。
しかしデカルト的な機械論がその後の唯物論の流れを強化したのも事実でしょう。
後輩の哲学者カントにも言えることですが、自分が編み出した哲学が本人の意図とは違ったかたちで後世に影響することもあります。
次回「デカルト(4)心は脳ではない」では、デカルト哲学の後世に対する影響について、僕の見解を交えながら解説したいと思います。