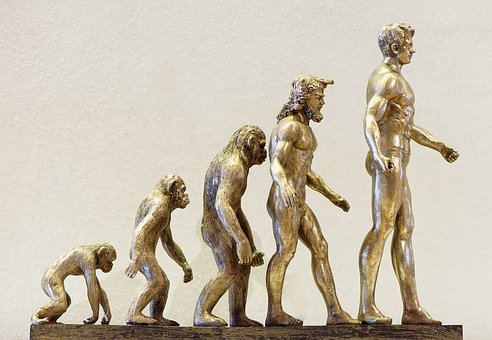前回記事「神の存在について(4)宇宙論的論証―後編」では、神の存在論証の1つである「宇宙論的論証」にまつわる諸問題を論じました。

ここ数回の記事で神の存在論証のうち「存在論的論証」と「宇宙論的論証」についてご説明したことになります。
今回からはさらに別の論証法をご紹介します。
ある意味で現代において最もホットな論争を招いている論証法だと言えるでしょう。
目的論的論証
その神の存在論証とは「目的論的論証」(Teleological Argument)と呼ばれるものです。
それはこの自然の「複雑さ」「精巧さ」を強調して「それほど複雑かつ精巧な自然には偉大なる設計者(つまり神)がいたはずだ」と論じるものです。
生物の身体などが典型的ですが、確かにこの大自然はとても精巧かつ複雑にできているように見えますよね。
生殖の仕組み、植物の光合成の仕組み、遺伝子を伝達してゆく仕組みなど、生物学のテキストでそれらのメカニズムを学ぶと、あまりにもよくできていて驚きを禁じ得ません。
生物の中には花びらそっくりのカマキリ、海底の砂や岩に化けるタコなど、他の捕食者を欺くために「擬態」するようなものまでいます。
花びらの形を知る「知性」があり、それに似せるようにカマキリの形態を変えようとする「意志」がなければ、確かに擬態という現象など起きない気がします。
母なる大自然を偏見のない目で眺めると「創造者の智慧」の働きを感じずにはいられません。そこから「自然物を設計した偉大な知性的創造者(神)がいる」と結論するわけです。
13世紀の神学者トマス・アクィナス(1225-1274)が「宇宙論的論証」を提示したことはご紹介しましたが、彼はこの「目的論的論証」も行っています。
トマスは現在も参照されるような神の存在論証の基本パターンを整理したんですね。
さらにイギリスの聖職者・哲学者であったウィリアム・ペイリー(1743-1805)は有名な「時計の類比」を使ってこの目的論的論証を世間に浸透させました。
↓↓↓↓↓↓
浜辺で精巧な時計を拾った人はそれを偶然の産物とは見なさず、当然それを設計・製作した人がいたと考えるはずだ。
時計を見た人がそれを設計した人の存在を想定するなら、時計以上に精巧なこの世界についてその設計者を想定するのは自然な考え方であろう。
↑↑↑↑↑↑
なるほど、説得力がある気がしますね。
ここで、これらの議論に関連する哲学用語を1つご紹介しておきましょう。
それは「合目的性」という言葉です。
例えばモグラの手は「土を掘る」という目的のために非常に都合よくできています。またハチの翅は「空中でホバリングする」という目的のために非常に都合よくできています。
このように事物のあり方が何らかの「目的」に合致していることを哲学ではよく「合目的性」と呼ぶのです。
普通は「そのようにしよう」という意志や知性が介在しなければこのような合目的性は生じないでしょう。
階段というものは人間が上の階へ移動するのにとても便利にできていますが、それは人間という知性ある存在が「そのように作ろう」と意志したからですよね。
合目的性と「意志」「知性」は1セットなわけです。
先ほどの定義を少し言い換えると「目的論的論証」とは、自然に「合目的性」が見られることを根拠として「自然には知性と意志を持つ設計者(神)がいる」と結論する議論のことなのです。
進化論の登場
この目的論的論証は長らく有力な神の存在論証であり続けました。
たとえ無神論者や懐疑論者でも、この目的論的論証を持ち出されると「そうは言ってもねえ、モゴモゴ……」と口ごもってしまうという感じだったのです。
確かに大自然の精巧さを「そりゃ偶然だ!」の一言で片付けるのは難しいでしょう。そんなことを言う方が知性を疑われてしまいかねません。
17世紀の科学革命と18世紀の啓蒙思想によって唯物論・無神論が台頭しましたが、目的論的論証が最後の砦となって無神論の拡大を防いでいた面があります。
ところが……です。
19世紀になるとこうした状況を一変させる出来事が起きます。
イギリスの生物学者チャールズ・ダーウィン(1809-1882)が『種の起源』を出版し、「進化論」が登場したのです。
これが革命的だったのは、「知性」や「意志」を持ち出すことなく、機械的・偶然的なプロセスだけで自然の合目的性を説明できると主張する考え方だったからです。
ダーウィン進化論が説明する「進化のメカニズム」とはどのようなものか、簡単にご説明しておきましょう。
↓↓↓↓↓↓
同じ生物種(例えばキリン)の中でも、それぞれの個体(1匹1匹)は身体の特徴に少しずつ違いがある(首が長い/短いなど)。こうした違いを「変異」と呼ぶ。
これらの違い(変異)はランダムな遺伝子変化によって生じるが、生存にとって有利な変異と不利な変異がある。
例えば「首が長い」という変異を持っているキリンは高い位置にある葉っぱも食べることができる。その結果、首が短いキリンよりも生き延びる確率が高くなる。
そして生き延びた首の長いキリン同士が交配することで、同じ特徴を持つ子孫のキリンの数が増えていく。一方、首の短いキリンは数が減っていく。
つまり有利な変異を持つものが言わば自然によって選ばれて生き残り、そうでないものは滅んでいく。これを「自然選択」と言う。
こうしてキリンの子孫たちは(徐々にだが)先祖たちよりも首が長い集団になっていく。
これを何百世代・何千世代と繰り返すと、新しい集団は元の集団とはまったく異なる「種」となっている。これが進化である。
↑↑↑↑↑↑
これが主流派の進化論者が説明する進化の仕組みです。
これによると、生物やその身体器官は「変異」と「自然選択」というメカニズムによって複雑な機能や構造を獲得したことになります。
なおダーウィンの時代には分子レベルでの遺伝学や生物学はまだ発展していませんでしたが、これらは後に進化論を補強する材料となります。
ダーウィンに由来する主流派の進化論は現在、遺伝学や分子生物学などを吸収して「ネオ・ダーウィニズム」などと呼ばれています。
神の「意志」「知性」がなくても自然は精巧になる?
繰り返しになりますが、この主流派進化論のポイントは「進化のプロセスに創造者(神)の知性や意志が介入してこない」ことです。
遺伝的な変異が起きるかどうかも偶然、その変異がどんなものであるかも偶然、その変異が生きる上で有利になるのかどうかも偶然です。
たまたま起きた変異がたまたま生存上有利になり、同じくたまたま似た変異を持つに至った個体と交配する。これの繰り返しで代を重ねるうちに形態などが徐々に変わっていく。
進化は言わば「勝手に起きる」わけですね。
上の方で述べた「合目的性」も進化論で説明できてしまいます。
モグラの手は土を掘るという目的に適合した形態をしていますが、これも慈悲深い神様が「よし、土を掘りやすい手に設計してあげよう」と考えたからではないことになります。
モグラの祖先の中にたまたま突然変異で土を掘りやすい手を獲得した個体たちがいて、それがたまたま生きるために有利だったから種として繁栄したというわけです。
花びらそっくりに擬態できるカマキリもそうです。偶然の遺伝子変化でその能力を得て生存上有利になったカマキリが多く繁殖しただけということになります。
一見、偶然とは思えない非常に精巧な仕組みでも「上のようなプロセスを何千万年・何億年と繰り返してゆけば実現する」と言われれば反論しにくくなるでしょう。
複雑で精巧で「合目的」的な大自然の妙技は、知性と意志を持つ創造主(神)を想定しなければどうしても説明できないもののように思われました。
ところがダーウィン進化論は、「意志」「知性」がなくとも複雑かつ精巧な自然ができあがるメカニズムを説明してしまいました。
これは神を信じる人々にとっては大変なことです。大自然はもはや「神の慈悲と全能」を証拠立てるものではないというのですから。
同時代に共産主義(=無神論の一種)を築いていたマルクスやエンゲルスは進化論の登場に大喜びしたそうです。
彼らに言わせれば「やった! ついに神の存在を守る最後の砦(目的論的論証)が崩されたぞ!」という感じでしょうか。
ダーウィン進化論は「神による創造」を否定する論拠を示し、正統派のキリスト教信仰に対しても大きなダメージを与えました。
そして進化論とマルクスの共産主義の2つは唯物論・無神論を支える主軸となって20世紀になだれ込んでいくことになります。
宗教に対する科学の勝利!
地動説以来の大戦果!
……と言いたいところですが、ことはそれほど単純ではありません。
日本の学問・メディア・教育・文化においては進化論が「常識中の常識」として扱われていますが、実はアメリカでは進化論の是非を巡って激しい論争が続いているんです。
そのことも日本では「アメリカには科学を否定する頑迷なキリスト教徒が多いんだよね~」くらいのノリで伝えられていますが、僕が見るところそういうものではありません。
むしろこれはアメリカ人の「理屈で納得できないものについては思考停止せずに疑問を持ち続ける」という健全な批判精神の現れだと思っています。
次回「神の存在(6)インテリジェント・デザイン(ID)とは?」では、このような進化論 vs. 反進化論の論争を(ほんの一部ですが)ご紹介したいと思います。

〈参考文献〉
・『「神」という謎[第二版]』(上枝美典著、2007、世界思想社)
・『科学と宗教』(A・E・マクグラス著、稲垣久和他訳、2009、教文館)