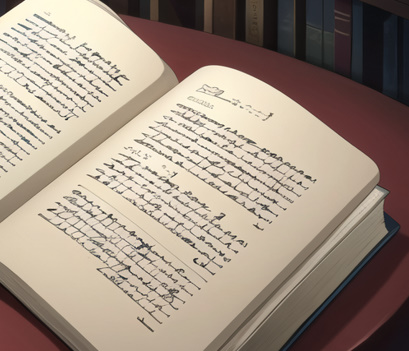前回記事では、書店に溢れる『サルでもわかる哲学』系の簡易本では、本当の意味で哲学を学べないと書きました。

それならば、大学の哲学科などに入学して本格的に学んでみるのはどうなのか?
このような疑問を持たれる方もおられるかもしれません。
実は、こと哲学に関しては、大学で学ぶことはあまりお勧めできません。
もちろん大学や先生によって違いはあるので一概には言えませんが、一般論として言わせていただけるなら、大学で習う哲学はすでに「オワコン」です。
「このit(イット)は何を指す?」で1時間も議論
僕がそう考える理由の1つは、大学での哲学研究が「文献学」あるいは「訓詁学」のようになっていることです。
訓詁学というのは、(例えば儒教などの)経典や書物に出てくる難しい言葉や文章の意味を解釈する学問です。
文献に向き合っているので、「文献学」と言ってもいいでしょう。
何をするのかと言えば、典型的なのが、「これ」「それ」「あれ」などの〈指示詞〉の検討です。
その文章に出てくる指示詞が一体何を指しているのか、「それ」ってどれなのか……。
こういうことですね。
確かにここをしっかり押さえておかないと、文章の意味を取り違えてしまうので、それが大事であることは分かります。
でも……、やりすぎなんです(^^ ;)
僕が大学院生だった頃、学生主体で自主的に勉強会をやっていたのですが、そこでやっていたのはまさに訓詁学でした。
フッサールという哲学者の著作『イデーン』(ドイツ語)を読んでいたのですが、指示詞を特定するためだけに、延々と1時間も議論したりするのです(ホントです)。
このdas(ダス:英語のitに当たる)は何を指す? 前文末尾のこれか? いや、4行前のこれじゃないか? そもそも指示詞じゃなくて関係代名詞かも?……等々。
そしてその日の成果はと言えば、『イデーン』のあるページの3行を訳せただけ……。こんなことがザラだったのです。
貴重な青春の時間を大いに浪費してしまいました(涙)
語学も訓詁学(文献学)も大事ではある。だがしかし……
誤解があってはまずいので断っておきますと、僕は語学や訓詁学・文献学そのものは非常に大切だとは思っているんです。
訓詁学と呼ぶかはともかく、「文献を正確に読解する」という技術は素晴らしいものでしょう。
しかしながら……
少なくとも哲学に関する限り、訓詁学・文献学は「手段」であって本質ではないのです。
哲学の本質とは、あくまで、学ぶ人の精神を高め、人格を陶冶する智慧の部分です。
訓詁学(専門的な文献解釈)も、どこかで誰かがやってくれている必要はあります。
解釈に困ったとき、「その社会のどこにも正しい読解ができる人がいない」というのでは確かに困りますから。
しかし、それはごくごく少数のエリートに任せておけばよろしいのです。
一般の大多数の人たちが学んで心の糧にすべきなのは、かみ砕いて易しく説かれた「哲学の本質」の方です。
- 死は終わりなのか。
- 心(魂)とは何か。
- 正しさとは何か。
- 善と悪はどのように定まるのか。
これらの普遍的な問題をないがしろにして、まるで語学や訓詁学が哲学の核心であるかのように考えるなら、本末転倒も甚だしいと言わざるを得ません。
今の状況だと、大学に数年間通っても、ちょっと英語や第二外国語が読めるようになるだけで終わりになる可能性が大です。哲学そのものはほとんど身に付かないでしょう。
大学での哲学研究・哲学教育は、「紙」(文献)を見るばかりで、世界や人間の「真理」の方を向いていないのです。
こういうわけで、智慧としての哲学を学ぼうとする者にとって、大学はいい環境とは言えません。そのわりに大金がかかり、時間と労力も要しますね。
それならばいっそ、哲学者たちの著作や、専門家による本格的な解説書・研究書にチャレンジする、つまり「独学」するというのはどうでしょうか?
僕も大学院を出てからは、ほとんど独学で新しい哲学分野を学んできました。
だから独学は必要ですが、同時にその大変さも身に染みています。
次回「マジで1文たりとも分からん! 哲学書の怪」では、その辺りの体験談をお話ししたいと思います。(了)
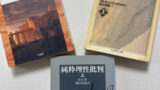
語学でも文献学でもない。心の糧となる「哲学の智慧」を目指すネット講座「プラトン・アカデミー」のご案内はこちら
↓↓↓↓↓↓