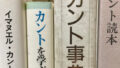これまで何度か、研究者や学者もなるべく「分かりやすい文章」を使うべきだという記事を書いてきました。

今回は、それに関連する、僕の記者時代の恥ずかしい話をしたいと思います。
僕の記者時代のお仕事
僕は大学院を出た後、ある月刊誌の編集部に入り、ライターとして自分で記事を書いたり、他の人が書いた記事をチェックしたりしていました。
また、その編集部が刊行する書籍の編集担当も時々やっていました。
その後、講師業に転身するわけですが、我ながら変わった経歴です(^^;)
さて、ある時、その雑誌と付き合いのある外部の識者(法律関係)による寄稿文を掲載することになり、僕がその方の文章をチェックする担当になったのです。
おそらく自分より20歳くらい上くらいの方でした。
そしてその文章は……。
申し訳ないのですが、読んでも意味がよく分からないものでした(汗)
専門用語が多いからとかではなく、明らかに日本語としておかしな文章なのです。
これは僕だけではなく、編集部の他の人たち(複数)も同じ意見でした。
ただ、そこまでなら問題ありません。別に、すべての日本人が分かりやすい文章を書けなければいけないということはありませんから。
問題はその後にありました。
文章のヘタさを絶対に認めない人
何があったかというと……。
文章に赤字で修正を入れて、ご本人のところへ持っていくと、大激怒されたのです(汗)
話しているうちにあちらもだんだんヒートアップしてきて、最後は周りに聞こえるような大声で怒鳴られるような感じになってしまいました。
もう完全なパワハラ……(T ^ T)
僕が失礼な言い方をしたわけではありません(多分……)。その方が短気なのは有名だったので、むしろ恐る恐る提案した感じです。
その方は、「他の用語を使えない理由」「この語はこの位置でないといけない理由」「この接続詞でないといけない理由」を実に理路整然と説明してくるのです。
でも僕に言わせれば、「単純にあなたの文章がヘタなだけ」なんです。
その方は多くの理由をあげましたが、すべて言い訳なのです。
その時に感じたのは「それなら、あなたと同じ専門知識があり、あなたと同じ内容を伝えようとする別人が書いたら、みんなこんな文章になるのですか?」ということです。
そう考えた時に「もっとうまい言い方がある」というなら、その文章には改善の余地があるということなのです。
文章なんて(音楽のメロディーと同じで)無限のパターンがあるのですから、「これしかあり得ない」ということ自体があり得ないはずでしょう。
最後には「お前らみたいな若いのと一緒にするな」みたいなことまで言い始めたので、編集部からもっと上の人にも出てもらいましたが、結局、修正は最小限に留まりました。
今後の関係もありますから、その時は編集部が妥協した格好になったのです。
難解な内容と易しい言葉の「異種結合」
僕や編集部の人たちは、分かりやすい文章を書かないと読者が減ってしまいますから、当然ですが、そう書けるようスキルを磨いていました。
1人が書いたものを全員で複数回チェックし、その都度、修正を入れます。
そうして、分かりやすい文章を書くトレーニングを自然とやっていたわけです。
大学や大学院で、学術論文らしく〈わざと〉難しい文章を書きまくっていた僕にとっては、最初はそれなりのカルチャーショックだったのを覚えています。
ところが、易しく書くことに慣れてくると、面白い現象が起きました。
上司や同僚から「とても論理的で分かりやすい、いい文章だ」とお褒めの言葉をいただけるようになったのです。
おそらく、学生時代にゴリゴリに論理的・学術的な文章を書いていたことが、いい方向に作用したのでしょう。
「なるべく隙のない論理的文章を書く」という下地があり、そこに「なるべく単純明快に書く」という技術をプラスできたからです。
内容的に複雑で難しいことでも、論理的に整理した上で、それをできる限り簡単な言葉で表現するよう心がけると分かりやすい文章になるのです。
これは、2つの種類の訓練をしたことで生まれた「異種結合」です。今では、これが僕の強みになっていると思うのです。
以上、恥ずかしい話も含めて、僕の文章修行についてお話しました。
簡単なことは簡単に。難しいことでも、なるべく簡単に。
このポリシーで哲学を伝えていきます。(了)
哲学の智慧を易しい言葉で解説!
完全独習型ネット哲学講座「プラトン・アカデミー」のご案内はこちら
↓↓↓↓↓↓