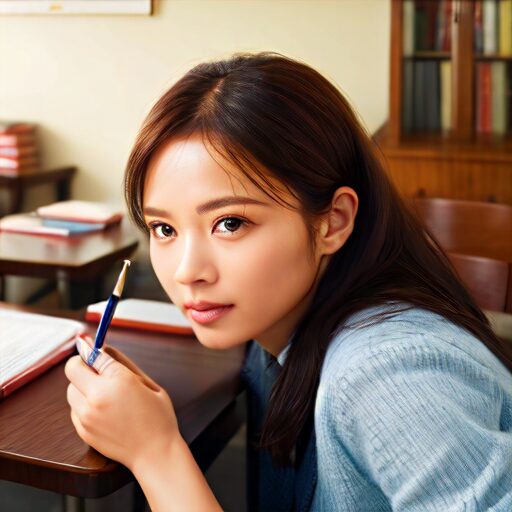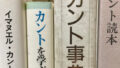僕は、哲学を学ぶために頭の回転や記憶力の良さは要らないと思っています。
哲学と言っても幅広いので、全般的に学ぼうとするなら、本を読み続ける「根気」と「考えようとする姿勢」は要るかもしれませんが、いわゆるIQ的な頭の良さは必要ないでしょう。
ただ、ちょっとだけ付け加えますと、予備知識のない人が哲学を学ぼうとする際に障害となってしまう事実が1つあるんです。
不必要に難しく書かれる哲学
それは、「哲学者本人たちや、その研究者たちによって、哲学が不必要なほど難しく書かれている」という事実です。
多くの人が身近なものとして哲学を学べるという未来にするためには、この「不必要な難解さのカベ」をクリアしないといけないわけですね。
いきなりですが、次の文章、意味が分かりますか?
① 汝の意志の格律が、常に同時に普遍的立法の原理として妥当するように行為せよ。
知らなければ「???」という感じではないでしょうか?
これ、簡単に言うと……
② みんなが真似しても大丈夫なマイルール(ポリシー)に従っていつも行動しなさい。
ただ単にこういう意味なんです。
例えば「腹が立ったら、目の前のやつをブン殴る。これが俺のやり方だ」なんていうジャイアンみたいなポリシーは迷惑ですね。
これをみんなが真似したら社会は崩壊してしまうでしょう。
これに対して「多少嫌なことがあっても、自制して行動しよう」というポリシーだったら、みんなが真似しても大丈夫です。
これは18世紀ドイツの哲学者カントの教えです。
実は、僕は大学・大学院とカント哲学を研究していました。
ただ今日、問題にしたいのは、この教えの内容ではありません。
①のような、ひどく難解な文章の書き方のほうです。
②のように書けばいいのに、①のように書くから意味不明で伝わらなくなります。
カントだけではありません。一般に哲学者たちはわざわざ難しい言葉を使う傾向があります(特にドイツ系の哲学者たち)。
こういう不必要に難解な文章が、一般の読者層を哲学から遠ざけていると思うのです。
また哲学を研究している現代の学者も同じような書き方をするため、一般読者と哲学との分離を助長しているのです。
学者たちの見栄と保身のせいで哲学が学べない
今さらカントを責めても仕方ないので、現代の話をしましょう。
僕が想像するに、現代の学者がわざと分かりにくい文章を書く理由は、「見栄」と「保身」なのではないかと思っています。
見栄というのはどういうことか。
科学などの理系の学問と違って、「文系の学問は目に見える成果が乏しい」という現実があります。哲学はその典型でしょう。
科学技術が日進月歩で進化していくおかげで、人々の生活がどんどん便利になり、人類の文明が発展していく……。
残念ながら、哲学にはこういうことがありません。
そこで哲学の研究者たちは「僕たちだって難しい学問をやってるんだ」「頭がいいんだ」ということをPRするために、難解な文章に走るというわけです。これは見栄ですね。
次に保身です。
哲学を難解なものにしておけば、それを「解説する」という仕事が発生します。
もし一般の人が自分で哲学の本を読んで、すぐに意味が理解できてしまえば、解説者は要りません。仕事がなくなってしまいます。
ラッキーなことに昔の哲学者の文章は難しいので、訓練を積んだ学者たちはそれを解読・伝達するという仕事ができます。
ついでに自分たちの研究書も難しく書いておけば、大学などで学生たちにそれを解説するという仕事ができるでしょう。
つまり厳しい言い方をすれば、自分たちの「飯のタネ」にするために、哲学をあえて難しいままにしておき、既得権益を守っているのです。
その結果、一般の人にとって、哲学が近づきにくい学問のままになっています。
僕は「プラトン・アカデミー」という完全独習型のネット哲学講座を運営していますが、それもこうした状況を何とかできないかと考えてのことです。
まだ公開しているサービスは少ないですが、レベルを落とすことなく、できるだけ難解な文章を避けて分かりやすく哲学を伝えることに心を砕いているので、ぜひチェックしてみて下さい。
↓↓↓↓↓↓

表現の問題はともかく、西洋哲学はとても意義深いものなので、僕の活動でその内容がなるべく多くの日本人の教養になるといいなと願っています。(了)